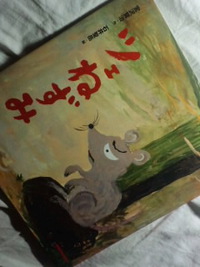2021年01月10日
依存について (心理的第三の思考若杉論)
依存について(・o・)ですが
今回は結論は ありません
ありません
まとめは あります
あります
主に概念的知識の
サイコエデュケーション・共通認識になります
参照文献は、精神医学特論or心理学あれこれに なっています。
なっています。
思考するための(=゜▽゜)ヒント になれば
になれば
 幸いです。
幸いです。
 ~
~ ~
~ ~
~ ~
~
● 病気or病状とは 当人がその事で不利益に成っていると気付く場合と、その事で当人が社会的な不利益が生じる場合。
当人がその事で不利益に成っていると気付く場合と、その事で当人が社会的な不利益が生じる場合。
(この事はE・クレペリンの言葉の引用ですが 若杉理解に
若杉理解に なってます。)
なってます。)
● 依存は 強迫的な欲求に対する「コントロール」喪失を特徴としており、強迫性障害群の関連は大きな問題である。
強迫的な欲求に対する「コントロール」喪失を特徴としており、強迫性障害群の関連は大きな問題である。
● 強迫の語には、
① ある概念や衝動が自分の意に反して執拗(しつよう)に意識にのぼり、
 ~
~ ~
~ ~
~ ~
~
次に(=゜▽゜)心理的な立場からの
思いに、思考を向けた心理学的な
サイコエデュケーション・共通認識の お話しです。
お話しです。
● 欲求 欲求は、生理的欲求・安全欲求・社会的欲求・尊厳欲求・自己実現欲求となっている。また
欲求は、生理的欲求・安全欲求・社会的欲求・尊厳欲求・自己実現欲求となっている。また
欲求の境は社会的と尊厳との間にあり、
生理的欲求・安全欲求・社会的欲求は、外的に充たされたい、欲求。
尊厳欲求・自己実現欲求は、内的に充たされた、欲求。
(マズローの欲求5段階説より)
● 錯覚 錯覚は、客観的に見れば「誤った認識」には違いない。
錯覚は、客観的に見れば「誤った認識」には違いない。
しかし そこには適応的な意味が見られる場合がある。
そこには適応的な意味が見られる場合がある。
このような認知的な調整が働くおかげで、
知覚は、そのものを意味ある対象として解釈するように働くのである。
(錯覚の科学より)
● ゼロリスクモデル 安全余裕度の概念で、一定の安全余裕度を維持している、という状況を示している。
安全余裕度の概念で、一定の安全余裕度を維持している、という状況を示している。
安全余裕度は 行動主体がハザード(危険源)から離れている、空間的・時間的距離と定義される。
行動主体がハザード(危険源)から離れている、空間的・時間的距離と定義される。
(交通心理学より)
● リスクホメオスタシス理論 ・個人ごとのリスクに対する許容値。
・個人ごとのリスクに対する許容値。
・状況がリスクの許容値を超えるとリスク回避の行動へ。
・許容値を下げるリスクテイキングをとる。
(交通心理学より)
● リスクテイキング 個人はリスクの許容値を一定にしようとする。
個人はリスクの許容値を一定にしようとする。
 注意
注意 行動の適応はリスクを高める方向にある。
行動の適応はリスクを高める方向にある。
(交通心理学より)
● レヴィンの公式 行動は人と環境との関数である。
行動は人と環境との関数である。
行為者自身に属する要因(内的要因)だけでなく、
その行為を行った際に、
行為者を、どのような環境が取り巻いていたかの(外的要因)も考慮に入れなければ、
十分な理解はできない。
行為者を取り巻く環境として重要なのは、
物理的環境よりも 社会的環境である。
社会的環境である。
社会的動物である人間にとって、
他者の存在は行動のみならず、
思考や感情にも影響を与える。
(心理学概論より)
この他にも(=゜▽゜)愛着の理論(人格心理学)の:愛着の内的ワーキングモデルや
認知心理学の記憶でのあれこれが必要になるのですが
話しが ややっこしく、
ややっこしく、 解り難くなるので
解り難くなるので
割愛 いたしました。
いたしました。
 ~
~ ~
~ ~
~ ~
~
これら共通認識 からの
からの
まとめの(=゜▽゜)第三の思考若杉論
依存とは 恐怖から逃れる為に取る為に、
恐怖から逃れる為に取る為に、
その人にとって安全・安心を与えてくれる、者や物とその行動。で
頼りにする。を過ぎる、度起こすと、依存です。
その境は「否定」が 境で
境で
 「このままじゃ駄目だ」の自己否定が出来る間は
「このままじゃ駄目だ」の自己否定が出来る間は
まだ、頼りにする。段階です
自分の不利益に自分が気付く
まるで(=゜▽゜)うつの症状に似た状態みたいな
これが進むと
完璧な 「否定」が起きます。
「否定」が起きます。
「私は悪くない」の「否定を否定する。」 完璧な「否定」です
完璧な「否定」です
この状態で、社会的不利益が生じているのですが
当人は「否定」が働いているので
『納得』はできません。
「私は悪くない」のですから
まるで(=゜▽゜)統合失調症のような、症状のようです。
自分では どうにもなりません、症状です
どうにもなりません、症状です
「私は悪くない」を支える
心理的要因は お話し致した通りです。また
お話し致した通りです。また
「私は悪くない」 状態になると
状態になると
恐くて始めた依存の原因、その
逃げたかったもの、
安全を確保していたもの、を
思い出す事が 出来なくなっています。
出来なくなっています。
忘れた訳では ありません
ありません
その証拠に(=゜▽゜)症状が改善して行くと
記憶が戻り 再燃することも、多多あります。
再燃することも、多多あります。
このままじゃ いかん。と
いかん。と
自己認識・出来たら
即、相談です
この時、必要なものと者は(=゜▽゜)リアルな
現実に、前に立つてる存在です。
そのひとに、依存するのでは なく
なく
そのひとに、任せる のです
のです
自分を変えられるのは 自分だけです。
自分だけです。
もとに戻るのではなく 有ることを受け入れ、それと、ともに逝くのです。
有ることを受け入れ、それと、ともに逝くのです。
以上
よんでいただきありがとう 御座いました。
御座いました。
 ~
~ ~
~ ~
~ ~
~
余談(=゜▽゜)ですが
多くの心理状況や状態を支えているのが
 思い込み
思い込み
で(=゜▽゜)思い込みの神髄が
「私は悪くない」です。
注意 「私が正しい」では
「私が正しい」では なく
なく
「私は悪くない」だから
平然と出来るのです。
「私が正しい」なら
我を張るので、周囲から反対されます、止められます。
また進むと
自分の事しかわからなくなり、
まだまだ進むと
自分で自分のことが 解らなくなるのです
解らなくなるのです
まるで(=゜▽゜)痴呆の様になります、そこで
周りが注意していなければ です。
です。
気に掛けてあげる。(b^ー°)たいせつです
今回は結論は
 ありません
ありませんまとめは
 あります
あります主に概念的知識の
サイコエデュケーション・共通認識になります
参照文献は、精神医学特論or心理学あれこれに
 なっています。
なっています。思考するための(=゜▽゜)ヒント
 になれば
になれば 幸いです。
幸いです。 ~
~ ~
~ ~
~ ~
~
● 病気or病状とは
 当人がその事で不利益に成っていると気付く場合と、その事で当人が社会的な不利益が生じる場合。
当人がその事で不利益に成っていると気付く場合と、その事で当人が社会的な不利益が生じる場合。(この事はE・クレペリンの言葉の引用ですが
 若杉理解に
若杉理解に なってます。)
なってます。)● 依存は
 強迫的な欲求に対する「コントロール」喪失を特徴としており、強迫性障害群の関連は大きな問題である。
強迫的な欲求に対する「コントロール」喪失を特徴としており、強迫性障害群の関連は大きな問題である。● 強迫の語には、
① ある概念や衝動が自分の意に反して執拗(しつよう)に意識にのぼり、
② 自分でも ばかばかしいと思いながらも、そうした観念・衝動やそれらを、
中和するための行為を止めることが できず、
③ これらをあえて抑えようとすると、
かえって強い不安が起きるという、
一連の現象を指して用いられる。
「~が!気になって仕方ない。」や「~しないと!気がすまない。」
といった日本語の言い回しは、こうした事情をよく表わしいる。
● 強迫行為は このような強迫観念を打ち消して
このような強迫観念を打ち消して
● 強迫行為は
 このような強迫観念を打ち消して
このような強迫観念を打ち消して 無害化するために行われる、ことが、多い。
● 依存には二つあり
心理的依存 「その物質を摂取したいという強い「欲求」があり、これを「コントロール」できないことを指す。また
「その物質を摂取したいという強い「欲求」があり、これを「コントロール」できないことを指す。また
心理的依存には、「否認」を伴うことも特徴であり、
否認とは 自分が引き起こしてる問題の大きさや、その事実そのものを認めようとしない、ものである。
自分が引き起こしてる問題の大きさや、その事実そのものを認めようとしない、ものである。
身体的依存 身体が、それ無しではバランスを保てなく成っている状態。
身体が、それ無しではバランスを保てなく成っている状態。
以上が(=゜▽゜)身体的な立場からの
見て解る、自分で気付く。精神医学特論からの抜粋で、
ベースとなる考え型 です。
です。
 重要なポイントは
重要なポイントは 「否認」と「欲求」それと「コントロール」です。
「否認」と「欲求」それと「コントロール」です。
● 依存には二つあり
心理的依存
 「その物質を摂取したいという強い「欲求」があり、これを「コントロール」できないことを指す。また
「その物質を摂取したいという強い「欲求」があり、これを「コントロール」できないことを指す。また心理的依存には、「否認」を伴うことも特徴であり、
否認とは
 自分が引き起こしてる問題の大きさや、その事実そのものを認めようとしない、ものである。
自分が引き起こしてる問題の大きさや、その事実そのものを認めようとしない、ものである。身体的依存
 身体が、それ無しではバランスを保てなく成っている状態。
身体が、それ無しではバランスを保てなく成っている状態。以上が(=゜▽゜)身体的な立場からの
見て解る、自分で気付く。精神医学特論からの抜粋で、
ベースとなる考え型
 です。
です。 重要なポイントは
重要なポイントは 「否認」と「欲求」それと「コントロール」です。
「否認」と「欲求」それと「コントロール」です。 ~
~ ~
~ ~
~ ~
~
次に(=゜▽゜)心理的な立場からの
思いに、思考を向けた心理学的な
サイコエデュケーション・共通認識の
 お話しです。
お話しです。● 欲求
 欲求は、生理的欲求・安全欲求・社会的欲求・尊厳欲求・自己実現欲求となっている。また
欲求は、生理的欲求・安全欲求・社会的欲求・尊厳欲求・自己実現欲求となっている。また欲求の境は社会的と尊厳との間にあり、
生理的欲求・安全欲求・社会的欲求は、外的に充たされたい、欲求。
尊厳欲求・自己実現欲求は、内的に充たされた、欲求。
(マズローの欲求5段階説より)
● 錯覚
 錯覚は、客観的に見れば「誤った認識」には違いない。
錯覚は、客観的に見れば「誤った認識」には違いない。しかし
 そこには適応的な意味が見られる場合がある。
そこには適応的な意味が見られる場合がある。このような認知的な調整が働くおかげで、
知覚は、そのものを意味ある対象として解釈するように働くのである。
(錯覚の科学より)
● ゼロリスクモデル
 安全余裕度の概念で、一定の安全余裕度を維持している、という状況を示している。
安全余裕度の概念で、一定の安全余裕度を維持している、という状況を示している。安全余裕度は
 行動主体がハザード(危険源)から離れている、空間的・時間的距離と定義される。
行動主体がハザード(危険源)から離れている、空間的・時間的距離と定義される。(交通心理学より)
● リスクホメオスタシス理論
 ・個人ごとのリスクに対する許容値。
・個人ごとのリスクに対する許容値。・状況がリスクの許容値を超えるとリスク回避の行動へ。
・許容値を下げるリスクテイキングをとる。
(交通心理学より)
● リスクテイキング
 個人はリスクの許容値を一定にしようとする。
個人はリスクの許容値を一定にしようとする。 注意
注意 行動の適応はリスクを高める方向にある。
行動の適応はリスクを高める方向にある。(交通心理学より)
● レヴィンの公式
 行動は人と環境との関数である。
行動は人と環境との関数である。行為者自身に属する要因(内的要因)だけでなく、
その行為を行った際に、
行為者を、どのような環境が取り巻いていたかの(外的要因)も考慮に入れなければ、
十分な理解はできない。
行為者を取り巻く環境として重要なのは、
物理的環境よりも
 社会的環境である。
社会的環境である。社会的動物である人間にとって、
他者の存在は行動のみならず、
思考や感情にも影響を与える。
(心理学概論より)
この他にも(=゜▽゜)愛着の理論(人格心理学)の:愛着の内的ワーキングモデルや
認知心理学の記憶でのあれこれが必要になるのですが
話しが
 ややっこしく、
ややっこしく、 解り難くなるので
解り難くなるので割愛
 いたしました。
いたしました。 ~
~ ~
~ ~
~ ~
~
これら共通認識
 からの
からのまとめの(=゜▽゜)第三の思考若杉論
依存とは
 恐怖から逃れる為に取る為に、
恐怖から逃れる為に取る為に、その人にとって安全・安心を与えてくれる、者や物とその行動。で

頼りにする。を過ぎる、度起こすと、依存です。
その境は「否定」が
 境で
境で 「このままじゃ駄目だ」の自己否定が出来る間は
「このままじゃ駄目だ」の自己否定が出来る間はまだ、頼りにする。段階です
自分の不利益に自分が気付く
まるで(=゜▽゜)うつの症状に似た状態みたいな
これが進むと
完璧な
 「否定」が起きます。
「否定」が起きます。「私は悪くない」の「否定を否定する。」
 完璧な「否定」です
完璧な「否定」ですこの状態で、社会的不利益が生じているのですが

当人は「否定」が働いているので
『納得』はできません。
「私は悪くない」のですから
まるで(=゜▽゜)統合失調症のような、症状のようです。
自分では
 どうにもなりません、症状です
どうにもなりません、症状です「私は悪くない」を支える
心理的要因は
 お話し致した通りです。また
お話し致した通りです。また「私は悪くない」
 状態になると
状態になると恐くて始めた依存の原因、その
逃げたかったもの、
安全を確保していたもの、を
思い出す事が
 出来なくなっています。
出来なくなっています。忘れた訳では
 ありません
ありませんその証拠に(=゜▽゜)症状が改善して行くと
記憶が戻り
 再燃することも、多多あります。
再燃することも、多多あります。このままじゃ
 いかん。と
いかん。と自己認識・出来たら
即、相談です
この時、必要なものと者は(=゜▽゜)リアルな
現実に、前に立つてる存在です。
そのひとに、依存するのでは
 なく
なくそのひとに、任せる
 のです
のです自分を変えられるのは
 自分だけです。
自分だけです。もとに戻るのではなく
 有ることを受け入れ、それと、ともに逝くのです。
有ることを受け入れ、それと、ともに逝くのです。以上
よんでいただきありがとう
 御座いました。
御座いました。 ~
~ ~
~ ~
~ ~
~
余談(=゜▽゜)ですが
多くの心理状況や状態を支えているのが
 思い込み
思い込みで(=゜▽゜)思い込みの神髄が
「私は悪くない」です。
注意
 「私が正しい」では
「私が正しい」では なく
なく「私は悪くない」だから
平然と出来るのです。
「私が正しい」なら
我を張るので、周囲から反対されます、止められます。
また進むと
自分の事しかわからなくなり、
まだまだ進むと
自分で自分のことが
 解らなくなるのです
解らなくなるのですまるで(=゜▽゜)痴呆の様になります、そこで
周りが注意していなければ
 です。
です。気に掛けてあげる。(b^ー°)たいせつです
タグ :Aiの為の心理学
頑張ってばかりもいられない 第三の思考若杉的には
薬の作用とその弱点 (第三の思考若杉論)
AIが具体化するのは心理学的なところまで。 (第三の思考若杉の経験論)
立ち上がるとき強くなる。 (第三の思考若杉論( ・∇・)手短にと思ってました。)
自己開放の仕方 開放されたその一時が大切なんだよ (第三の思考若杉論)
追いつく事はできなが追い越していることはある。 (第三の思考若杉の経験論)
薬の作用とその弱点 (第三の思考若杉論)
AIが具体化するのは心理学的なところまで。 (第三の思考若杉の経験論)
立ち上がるとき強くなる。 (第三の思考若杉論( ・∇・)手短にと思ってました。)
自己開放の仕方 開放されたその一時が大切なんだよ (第三の思考若杉論)
追いつく事はできなが追い越していることはある。 (第三の思考若杉の経験論)
Posted by わかわ at 16:24│Comments(0)
│今日わかったこと